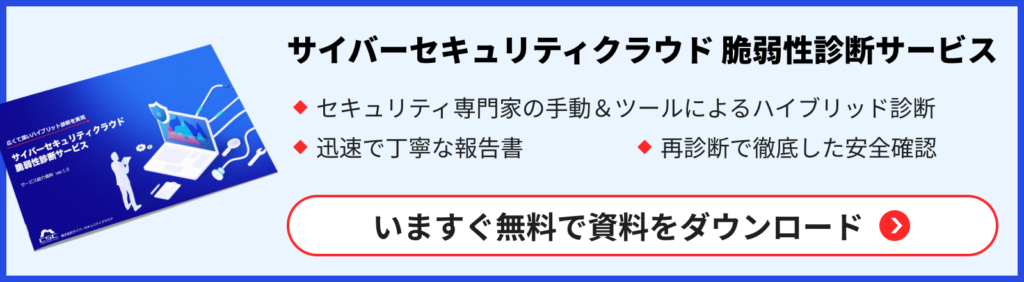Webアプリケーション脆弱性診断が求められる背景と目的
Webアプリケーション脆弱性診断は、単に脆弱性の有無を調べるだけでなく、サイバー攻撃による被害を未然に防ぎ、システムの安全性を継続的に高めることを目的としています。
ECサイトや会員制サービス、SaaSなど、Webを通じて顧客情報や取引データを扱う企業が増える中で、Webアプリケーションは攻撃者にとって格好の標的となっています。Webサイトを公開した直後から自動スキャンによる攻撃を受けるリスクがあり、脆弱性診断を行わない状態は「常に攻撃対象になり得る環境」ともいえます。
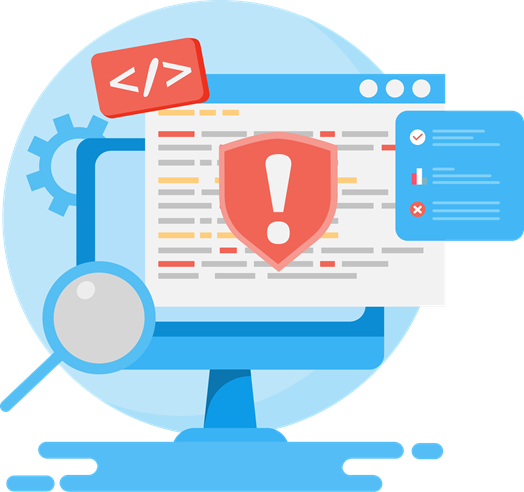
また、法令や業界ガイドラインで脆弱性診断の実施が求められるケースや、ISMS認証・取引先契約時に報告書提出を条件とされるケースも増えており、企業活動における“必須要件”としての位置づけが強まりつつあります。
▼お役立ち資料「失敗しないWebアプリケーション脆弱性診断の選び方」ダウンロード!
失敗しないWebアプリケーション脆弱性診断の選び方 ~依頼時のポイントから報告書活用まで解説~
そもそもWebアプリケーションとは?
Webアプリケーションとは、インターネットを介してWebブラウザ上で動作するソフトウェアを指します。ユーザーはインターネット環境さえあれば場所やデバイスを選ばずに利用でき、利便性が高いことから幅広く普及しています。
代表例:Gmail、YouTube、ECサイト、SaaSサービスなど
Webアプリケーションはサーバやデータベース、APIと連携して動作するため、フロントエンドだけでなくバックエンド部分にも脆弱性が潜む可能性があります。つまり、企業のサービス提供の基盤である一方で、攻撃者にとって格好の狙い目にもなりやすい仕組みを含んでいるのです。
なぜWebアプリケーションが攻撃対象になるのか
Webアプリケーションが攻撃対象となる最大の理由は、インターネットに公開され、誰でもアクセス可能であることです。
- 公開部分は常に露出しているため、攻撃者が容易に調査・攻撃できる
- Webサービスを提供する企業が増えており、規模に関わらず無差別に攻撃を受けるリスクがある
- 1つの脆弱性を突かれるだけで、顧客情報や社内システムへの入口になり得る
実際、過去には脆弱性を悪用したインシデントが多数発生しており、その多くは企業規模に関係なく被害を受けています。
「脆弱性診断」について詳しくはこちらもチェック!
脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?やり方や種類から、失敗しない選び方までを解説
Webアプリケーションに起因するインシデント例
以下は、代表的なWebアプリケーションに起因するインシデント事例です。
| 業界・サービス種別 | 被害内容 |
| 住宅業界の会員サイト | SQLインジェクション攻撃被害により、会員情報やログイン情報が外部に漏洩。最大46万件超の個人情報が影響(2024年5月) |
| スポーツ団体の公式サイト | サイトが改ざんされ、利用者が偽の通販サイトやブラウザ更新を装う不正ページに誘導される被害が発生。復旧が難航し、仮設Webサイトで情報発信を行った(2025年5月) |
| 教育関連クラウドサービス | 利用者認証システムが突破され、不正アクセスによりIDや暗号化済みパスワードなど利用者情報が流出する可能性を 公表(2020年4月) |
これらの事例は、Webアプリケーションの脆弱性 や設定不備が攻撃経路となり得ることを示しています。
こうした被害は、企業の信用失墜や売上減少だけでなく、法令違反や取引停止など事業における重大な影響を受けます。
Webアプリケーション脆弱性診断で分かるリスク
Webアプリケーション脆弱性診断を実施することで、潜在的なセキュリティ上の欠陥と、その欠陥が攻撃者に悪用された場合に発生し得る被害の種類を明確に把握できます。
ここでは、代表的な脆弱性と国際的に参照される「OWASP Top 10」について解説します。
代表的な脆弱性と国際基準「OWASP TOP 10」について
Webアプリケーションの代表的な脆弱性は、国際的に共有されている「OWASP Top 10」にまとめられています。OWASP Top 10は、世界中のセキュリティ専門家が収集した攻撃事例をもとに作成されたリストであり、Webアプリケーション開発やセキュリティ診断における基準として広く利用されています。
OWASP Top 10(2021版)一覧※
- アクセス制御の不備(Broken Access Control)
- 暗号化の失敗(Cryptographic Failures)
- インジェクション(Injection)
- 安全が確認されない不安な設計(Insecure Design)
- セキュリティ設定のミス(Security Misconfiguration)
- 脆弱で古くなったコンポーネント(Vulnerable and Outdated Components)
- 識別と認証の失敗(Identification and Authentication Failures)
- ソフトウェアとデータの整合性の不具合(Software and Data Integrity Failures)
- セキュリティログとモニタリングの失敗(Security Logging and Monitoring Failures)
- サーバサイドリクエストフォージェリ(Server-Side Request Forgery:SSRF)
※2025年10月現在の最新版
代表的な脆弱性としてまず挙げられるのがインジェクションです。入力フォームや検索欄に不正なコードを埋め込まれることで、データベースに意図しない命令が実行され、情報が改ざんされたり漏えいしたりするリスクがあります。実際に94%のアプリケーションで何らかのインジェクションに関する問題が確認されており、その中でもクロスサイトスクリプティング(XSS)、SQLインジェクション、ファイル名やパス名の外部制御が代表的です。
さらに、アクセス制御の不備があると、本来権限を持たない利用者が機密情報や管理機能にアクセスでき、情報漏えいや不正操作につながります。
最後に、セキュリティ設定のミスも多くの企業で見られる問題です。管理画面の認証設定不足や不要ポートの開放、デフォルト設定のままの運用などが原因となり、攻撃者に侵入のきっかけを与えてしまいます。
Webアプリケーション脆弱性診断はいつ実施すべき?
Webアプリケーション脆弱性診断は、一度実施すれば終わりではなく、状況やタイミングに応じて継続的に行うことが重要です。
代表的な3つのタイミングを整理します。
新規サービス・サイトのリリース前
新規にWebサービスやWebサイトを公開する際には、リリース前に脆弱性診断を実施することが推奨されます。開発段階では、コーディング時のセキュリティ要件漏れや設定ミスが発生する可能性があり、これらは実装後に気づきにくい傾向があります。リリース後に脆弱性が見つかると、顧客情報の漏えいやサイト改ざんにつながり、初期段階からブランド信頼を損ねる恐れがあります。公開前に診断を行うことで、修正コストを抑えつつ安全性を高めた状態でリリースできる点が大きなメリットです。
定期的な診断
一度診断を実施しても、システムやサービスは運用を続ける中で更新や改修が行われます。そのたびに新たな脆弱性が生じる可能性があるため、定期的に診断を行うことが欠かせません。特に、利用しているフレームワークやコンポーネントにセキュリティ更新が入る場合には、早期の診断が効果的です。目安としては年1回以上の定期診断が望ましいとされています。
法令や監査対象、取引先からの要求時
個人情報保護法や業界ガイドラインに基づく規制、またはISMS(情報セキュリティマネジメントシステム認証)に関連する監査対応の一環として、脆弱性診断が求められるケースがあります。さらに、取引先との契約条件として診断結果の報告書提出を求められる場合も少なくありません。
法令遵守や取引の継続に直結することもあるため、脆弱性診断実施を前提にスケジュールや予算をあらかじめ確保しておくことが重要です。
Webアプリケーション脆弱性診断の種類
Webアプリケーション脆弱性診断には、大きく分けて「ツール診断」と「手動診断」があり、それぞれに特徴と役割があります。
ここでは両者の違いやメリット、代表的な診断項目について解説します。
ツール診断
専用のセキュリティツールを用いて自動的に脆弱性を検出する方法です。
診断対象に対して疑似的な攻撃を行い、脆弱性の有無を確認します。短時間で広範囲をカバーでき、定期的な診断やコストを抑えた一次調査に適しています。
ただし、検知結果に誤検知や見逃しが含まれる場合があり、特に複雑なアプリケーション固有の挙動は検出が難しいケースがあります。
「ツール診断」について詳しくはこちらもチェック!
脆弱性診断ツールとは?特徴や気を付けたいポイントも解説!
手動診断
セキュリティエンジニアがアプリケーションの構造や仕様を把握したうえで、実際の攻撃手法をシミュレーションしながら脆弱性を確認する方法です。
認証機能や権限管理など、ツールでは検出が難しい領域に強みがあります。
その一方で、診断に時間とコストがかかるため、プロジェクトの重要度やリスクに応じて適切に選択する必要があります。
「手動診断」について詳しくはこちらもチェック!
手動脆弱性診断の特徴とは?脆弱性診断における優位性と費用を解説!
ツール診断と手動診断の違いとメリット
ツール診断は短時間で広範囲を調べるのに適しており、手動診断は精度の高い検証に強みがあります。両者の特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。
- ツール診断:スピードと網羅性に優れる。定期チェックや簡易診断に向く。
- 手動診断:精度が高く、複雑な脆弱性を発見できる。本番リリース前や高リスクシステムに有効。
両者を組み合わせたハイブリッド診断では、網羅性と精度を両立でき、より実効性の高い診断が可能になります。
Webアプリケーション脆弱性診断の代表的な診断項目
代表的な診断項目には次のようなものがあります。
- 入力値検証の不備(SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなど)
- 認証・認可の不備(パスワード強度不足、セッション管理の欠陥、権限昇格のリスク)
- セキュリティ設定ミス(不要なポートの開放、管理画面へのアクセス制御不足)
- 暗号化の不備(通信経路の平文送信、古い暗号化アルゴリズムの利用)
- その他の脆弱性(ディレクトリトラバーサル、ファイルアップロード機能の不備など)
どこまでやれば十分?診断範囲の判断基準と考え方
Webアプリケーション脆弱性診断を検討する際に、多くの担当者が悩むのが「診断範囲をどこまで設定すべきか」という点です。範囲が広すぎればコストや工数が膨らみ、狭すぎればリスクが残ります。
ここでは、範囲設定の基本的な考え方と、リソースや予算に応じた現実的な判断方法を紹介します。
診断範囲の決め方
診断費用は、対象となるページ数や機能の多さによって大きく変動します。
そのため、すべてを一度に診断するのではなく、リスクの高さ(認証機能や決済機能、会員情報入力フォームなど)に応じて優先順位をつけて対応することが重要です。
診断範囲を決める際には、次の観点が役立ちます。
- 公開範囲の広さ:
外部からアクセス可能な部分は、攻撃対象になりやすいため優先的に診断する必要があります。 - 重要データの有無:
会員情報や決済データを扱う部分はリスクが高く、重点的な診断が求められます。 - システム構成の複雑さ:
API連携や外部サービスとの接続が多いほど攻撃経路が増えるため、診断範囲も広げる必要があります。 - リリースや改修のタイミング:
新規リリースや大規模アップデート時には、変更部分を中心に診断を行うのが効果的です。
社内リソースや予算に応じた考え方
診断は理想的にはシステム全体を対象とするのが望ましいですが、現実には社内リソースや予算の制約があります。そのため、以下のような考え方で優先順位をつけると効果的です。
- リスクの高い部分から着手する:
会員登録・ログイン・決済など、攻撃による影響が大きい機能を優先。 - ツール診断と手動診断を組み合わせる:
広範囲はツール診断で網羅し、重要部分は手動診断で精査する。 - 年間予算を考慮した分割実施:
一度に全範囲を診断せず、年度ごとに重点箇所を切り分けて計画的に実施する。
こうした判断を行うことで、限られた予算や人員でも、効果的にセキュリティリスクを低減することが可能になります。そのため、「やらないリスク」と比較しながら、自社の体制や予算に合った診断を実施することが大切です。
「脆弱性診断の見積の考え方」についてこちらもチェック!
脆弱性診断の見積もりの考え方とは?動的ページのカウント方法を解説!
脆弱性診断会社の選び方
診断範囲や予算の目安を決めたら、次に重要になるのが「どの会社に依頼するか」です。脆弱性診断は提供会社ごとに手法やサポート内容が異なるため、信頼できるパートナーを選ぶことが効果的な対策につながります。
ここでは、診断会社を選定する際の3つのポイントを紹介します。
実績と信頼性
診断会社の信頼性を判断するうえで、これまでに診断を行った企業数や業種の幅は重要な指標です。金融、医療、ECなど幅広い業界での実績があれば、多様な脅威に対応できるノウハウを有している可能性が高まります。また、情報セキュリティに関する認証(例:ISMS認証)を取得しているかどうかもチェックポイントとなります。
さらに、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」を確認するのもおすすめです。
このリストは、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」に適合していると認められたサービスをまとめたもので、信頼性の高い脆弱性診断サービスを選ぶ際の客観的な判断材料となります。
事例や顧客の声が公開されていれば、自社と類似したシステムを持つ企業の事例を参考にするのも有効です。
提供する診断手法の精度と診断項目の網羅性
診断会社によっては、自動ツールのみを利用するケースや、人による詳細な手動診断までカバーするケースなど、手法が大きく異なります。両方のメリットを兼ね備えたハイブリッド診断を提供しているかどうかも確認するとよいでしょう。
さらに、OWASP Top 10に含まれる代表的な脆弱性や、近年増加している最新の脆弱性を網羅的に検証できるかも確認すべきポイントです。
サポート体制と再診断の有無
脆弱性診断は「実施して終わり」ではなく、発見された脆弱性を修正し、安全性を確保することが最終目的です。そのため、診断後に改善方法を提示するサポート体制が整っているかどうかが重要です。
また、修正後に再度診断を行い、脆弱性が解消されていることを確認できるサービスがあるかどうかも確認しましょう。さらに、自社の特性に合わせて診断内容や報告書をカスタマイズできる柔軟性があるかも重要な選定ポイントです。
Webアプリケーション脆弱性診断なら
「サイバーセキュリティクラウド脆弱性診断サービス」
サイバーセキュリティクラウドのWebアプリケーション脆弱性診断は、OWASP Top 10を網羅した幅広い診断項目に対応しており、経済産業省の「情報セキュリティサービス基準」にも適合しています。第三者への説明に活用できる、詳細な脆弱性報告書を提供しています。
報告書には、全体のリスクを俯瞰できる総合評価と、個別の脆弱性ごとの詳細な解説を組み合わせており、発見された課題に対する具体的な対策方法も丁寧に記載しています。
診断で終わらず、改善につなげることを重視した構成のため、再発防止やセキュリティレベルの継続的な向上に直結する内容となっています。
主な特徴
- 25年以上の診断実績と専門エンジニアによる手動検証を含むハイブリッド診断
- 再診断1回無料で、修正後の安全性を確認可能
- 迅速な報告書提出(最短5営業日)で、社内報告や取引先への提示に対応
- IPAリスト準拠、OWASP基準に基づいた診断で、国際的な信頼性を確保
- セッション管理や認証機能なども含め、幅広い診断項目に対応
- Webアプリケーションのセキュリティ分野で豊富な実績を持つ日本発のセキュリティメーカー
開発中・運用中のWebアプリケーションにおける脆弱性診断や、ISMSやIPO関連で診断結果のエビデンスが必要な場合に最適です。Webアプリケーションに加え、プラットフォーム診断やAPI診断も選択できます。