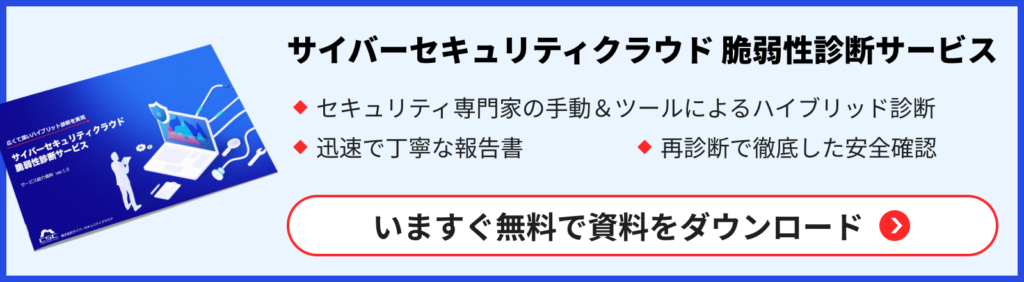脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?
脆弱性診断(セキュリティ診断)は、サーバやWebアプリケーションに存在するセキュリティ上の弱点を発見するための検査で、攻撃の侵入口となる脆弱性を網羅的にチェックします。
サーバ構成、アプリケーションの動作など、システム全体を対象に既知の脆弱性パターンに基づいて調査を行います。従来のオンプレミス環境や、AWS等のクラウドサービス上のシステムでも実施可能です。
検査基準としては、OWASP(Open Web Application Security Project)が公開している「OWASP Top 10」などの国際的なガイドラインや、IPA(情報処理推進機構)が提供する「安全なウェブサイトの作り方」などの国内基準に沿って実施されることが一般的です。
脆弱性診断の費用は診断対象の規模や範囲により異なり、一般的なWebアプリケーション診断の場合で50万円から200万円程度です。診断期間は通常2〜4週間程度で実施可能です。
合わせて読みたい:「脆弱性診断とは?」
脆弱性診断(セキュリティ診断)の目的
脆弱性診断の主な目的は、システムやWebサイトに潜む脆弱性を早期に発見し、対策を講じることです。専門的な知識と経験を持つセキュリティ専門家やツールを利用して、最新の攻撃手法や脆弱性情報を踏まえてシステムを検査し、潜在的なリスクを可視化します。
脆弱性診断を実施することで得られるメリットは主に2つあります。
まず、1つ目にセキュリティリスクを定量的に評価できるため、対策の優先順位付けが可能になります。例えば、システムのリリース前に診断を行うことでセキュリティ事故やデータ漏えいのリスクを大幅に低減できます。
2つ目に、脆弱性診断を定期的に行うことで、システム改修やアップデート後に新たな脆弱性が発生していないかを確認できます。システム開発においては、新機能の追加や既存機能の修正が頻繁に行われますが、こうした変更が意図せずセキュリティホールを生み出すことがあります。特に開発チームとセキュリティチームが分離している組織では、開発段階でセキュリティが十分に考慮されないケースも少なくありません。定期的な診断は、こうした「知らないうちに生まれた脆弱性」を発見するための重要な手段です。
特にWebサイトは、定期的なコンテンツ更新や機能追加によって新たな脆弱性が生じやすいため、年に1回以上の診断実施が推奨されています。Webサイトは企業の顔であると同時に、顧客情報や決済情報など重要なデータを扱うケースも多く、攻撃者にとって魅力的な標的となっています。だからこそ、システムの安全性を確保し、ビジネスの信頼性を維持するためには、計画的かつ継続的な脆弱性診断が必要不可欠なのです。
ペネトレーションテスト(侵入テスト)とは?
脆弱性診断(セキュリティ診断)と混同されがちなのがペネトレーションテストです。
ペネトレーションテストとは、実際のハッカーと同様の手法を用いて、システムやネットワークへの侵入を試みるテストです。脆弱性診断よりも踏み込んだ内容で、発見された脆弱性を実際に悪用して侵入できるかどうかを確認します。
技術者が攻撃者の視点から実際の攻撃手法を用いてシステムの防御を突破しようと試みるため、単なる脆弱性の発見にとどまらず、その脆弱性が実際に悪用可能かどうか、また攻撃に成功した場合にどのような被害が生じる可能性があるかを実証的に確認できます。
ペネトレーションテストの費用は、対象システムの規模や複雑さによって異なりますが、一般的に200万円〜500万円以上かかることが多く、実施期間も数週間から数ヶ月に及ぶことがあります。高度なセキュリティが求められる金融機関や重要インフラなどでは、ペネトレーションテストを実施することが一般的です。
ペネトレーションテストの目的
ペネトレーションテストの主な目的は、実際の攻撃者の視点からシステムのセキュリティレベルを評価することです。ペネトレーションテストで得られるメリットは主に3つあります。
まず1つ目に、実際のサイバー攻撃では、単一の脆弱性だけでなく、複数の脆弱性を組み合わせた高度な攻撃手法が用いられることが多いため、ペネトレーションテストではそうした複合的な攻撃に対する耐性を検証します。
2つ目に、既に導入されているセキュリティ対策が実際の攻撃に対して有効に機能するかどうかを実証的に確認することも重要な目的です。例えば、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)やIDS(侵入検知システム)などの防御システムが、巧妙な攻撃手法に対しても迅速に検知できるかどうか、ログ分析システムやセキュリティ監視はうまく機能するか確認します。さらに、万が一侵入を許してしまった場合の被害が拡大する可能性も検証し、どこまで影響が出るかを評価します。
ペネトレーションテストは、侵入経路の確認とどこで侵入を遮断すべきか判断でき、新たなセキュリティ投資の優先順位付けに役立ちます。限られたリソースの中で最も効果的なセキュリティ投資を行うためには、実際の攻撃シナリオに基づいたリスク評価が不可欠です。
脆弱性診断とペネトレーションテストの違い
脆弱性診断(セキュリティ診断)とペネトレーションテストは、システムのセキュリティ上の問題を発見するという点では共通していますが、実施方法に大きな違いがあります。以下で詳しく説明していきます。
脆弱性診断は「チェック」
脆弱性診断は、システムやアプリケーションのセキュリティ上の弱点を特定する「チェック」作業です。企業が以下のような状況の場合、脆弱性診断の実施をおすすめします。
Webサイトやオンラインサービスを運営し、顧客の個人情報や決済情報を扱っている企業は特に重要です。システムの改修やアップデートを定期的に行っている企業も、新たな脆弱性が生じていないか確認する必要があります。また、取引先や業界団体からセキュリティ証明を求められている企業にとっても、脆弱性診断は必須の対策となっています。
脆弱性診断では、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングといった一般的な脆弱性から、設定ミスやパッチ適用状況まで幅広く検証します。特に自社内にセキュリティ専門家がいない企業では、ツール診断と手動診断の組み合わせたハイブリッド診断が効果的です。
診断結果は分かりやすいレポートとして提供されるため、IT部門だけでなく経営層も含めたセキュリティリスクの共有と、対策の優先順位付けに役立ちます。自社の資産と信頼を守るために、定期的な脆弱性診断を検討するとよいでしょう。
ペネトレーションテストは「演習」
ペネトレーションテストは、前述の通り実際の攻撃を模擬した「演習」です。以下のような企業にとって、ペネトレーションテストの実施をおすすめします。
金融機関や医療機関など、高度な機密情報を扱う企業では、単なる脆弱性の発見だけでなく、実際に攻撃者が侵入できるかどうかを検証することが不可欠です。また、重要インフラを運営する企業や、サイバー攻撃による業務停止が社会に大きな影響を与える企業にとっても、実践的な防御力を確認するペネトレーションテストは必須の対策となっています。さらに、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)などの厳格なコンプライアンス要件が適用される企業も、定期的なペネトレーションテストが求められることが多いでしょう。
ペネトレーションテストでは、熟練のセキュリティ専門家が実際の攻撃者と同じ思考と技術で、システムへの侵入を試みます。彼らは複数の脆弱性を組み合わせた高度な攻撃シナリオを構築し、時には社会工学的手法も取り入れながら、あらゆる侵入経路を探ります。
テスト結果は詳細な報告書としてまとめられ、成功した攻撃手法や潜在的な被害範囲が明確に示されます。この報告書は高度に専門的な内容になることが多く、解釈や対策立案には専門知識が必要です。また、SOC(セキュリティ監視)やCSIRT(インシデント対応)体制の強化にも活かせます。実際の攻撃シナリオに基づいたテスト結果を分析することで、監視すべきポイントや迅速な対応が必要な状況の把握が可能になります。自社の防御が本当に機能するのか、実践的に確認したい企業は、ペネトレーションテストを検討してみてはいかがでしょうか。
脆弱性診断とペネトレーションテスト、どちらを選ぶべきか?
多くの企業では、脆弱性診断とペネトレーションテストのどちらを実施すべきか迷うことがあります。選択の基準となるポイントを2つ紹介します。
1つ目は、セキュリティ対策の初期段階にある企業には脆弱性診断が最適です。比較的低コストで実施でき、基本的なセキュリティリスクを効率的に把握できます。セキュリティテストの経験がない企業や予算に制約がある場合は、まず脆弱性診断から始めましょう。定期的な実施が可能なため、継続的なセキュリティ管理の基盤となります。
2つ目は、脆弱性診断は実施済みで、より高度なセキュリティが必要なシステムにはペネトレーションテストが適しています。金融データや個人情報など重要な情報を扱うシステムや、既に基本的なセキュリティ対策が整っている企業におすすめです。実際の攻撃者の視点から防御力を検証できる点が大きな強みです。
最も効果的なアプローチは段階的な実施です。まず脆弱性診断で基本的な弱点を見つけて対処し、その後重要なシステムに対してペネトレーションテストを行うという流れが理想的です。ただし、業界規制やコンプライアンス要件で特定のテストが求められている場合は、それに従うことが必要です。
自社のセキュリティニーズ、システムの重要度、予算を考慮して、最適なセキュリティテストを選択しましょう。
侵入リスクは脆弱性診断でも把握できる
サイバー攻撃の大半は既知の脆弱性を悪用したものです。脆弱性診断により、こうした基本的な攻撃経路を特定し、対策を講じることで、多くの侵入リスクを効果的に低減できます。
対象のサーバや特定のアプリケーションなどに対し、脆弱性を悪用して「侵入できるか」の調査をするのであれば、脆弱性診断でも十分に行えます。特にOSコマンドが実行可能な脆弱性が存在する場合には、その脆弱性の発見と対策によって侵入を防ぐ目的は達成できるため、必ずしも高コストなペネトレーションテストが必要ではなく、脆弱性診断のみの実施で問題ありません。
脆弱性診断(セキュリティ診断)サービスなら
「サイバーセキュリティクラウド脆弱性診断サービス」
ハイブリッド診断で効果的な脆弱性診断を実施するなら、25年以上の豊富な診断実績を持つサイバーセキュリティクラウドの脆弱性診断サービスをおすすめします。サイバーセキュリティクラウドの脆弱性診断サービスには以下のような特長があります。
・セキュリティ専門家による手動診断とツール診断を組み合わせたハイブリッド診断・セキュリティ専門家が最適な診断計画を提案してくれる
・分かりやすい診断報告書を提出してもらえる
・無料再診断と専門家サポートが付帯されている
セキュリティ対策は一度実施して終わりではなく、継続的な取り組みが重要です。サイバーセキュリティクラウドの脆弱性診断サービスは、診断後のフォローアップサポートも充実しており、脆弱性対策の支援や再診断なども含めた包括的なセキュリティサービスです。