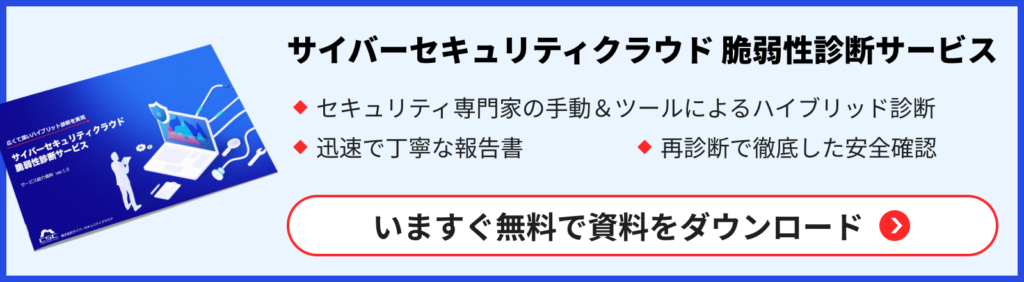手動診断のやり方
手動診断は、セキュリティ専門家がWebアプリケーションやサーバの挙動を実際に操作しながら脆弱性を調査する手法です。まずは、システムの管理者へのヒアリングなどを通じて対象システムに関する診断範囲や構成の確認をします。対象となるページ、機能、ログインの有無などシステムの全体像を把握した上で、診断計画を策定します。
次に、収集した情報をもとにセキュリティ専門家が手動で検証を行っていきます。たとえば、ログイン処理や入力フォームに対して意図的に不正な値を送信し、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの脆弱性が残っていて情報漏えいの可能性がないか確認します。また、異なる権限設定が正しく機能しているか、管理者権限の機能に一般ユーザーがアクセスできないかといった、認証・認可の挙動も重点的に検証し、アカウントやシステムが乗っ取られる可能性を確認します。

セッション管理についても重点的に検証します。ログイン後のセッションIDが安全に管理されているか、ログアウト時にセッションが無効化されているかなどを確認し、不正アクセスのリスクがないかを確認します。こうした検証はシステムの仕様やユーザーの操作フローを理解した上で行われるため、ビジネスロジックに依存した脆弱性を発見することができます。
診断の最終段階では、発見された脆弱性ごとにリスクの影響度や再現手順を整理し、報告書としてまとめて提出されます。報告書には、脆弱性の内容だけでなく、具体的な改修方法や対策方針も記載され、開発者がスムーズに修正を進められるよう配慮されています。必要に応じて、システム修正後に再診断を行う場合もあります。
手動診断の特徴
手動診断には、ツール診断にはない特徴があります。最大の特徴は、セキュリティ専門家の知見を活かしながら診断を行う点です。特にWebアプリケーションの認証・認可やビジネスロジックに深く関わる欠陥は、ツール診断のスキャンだけでは見落とされがちですが、手動診断なら検出可能です。
また、手動診断では専門家が一つひとつ検証するため、報告される脆弱性は実際に検出され問題があると判断されたものとなることも特徴です。ツール診断は誤検知(False Positive)を含むことがありますが、手動診断では誤検知の可能性は限りなく低くなります。
一方で、手動診断は人手による細やかで高度な検証を行う分、診断にかかる日数が長くなる傾向があり、ツール診断と比べて費用もやや高めの診断方法となります。そのため、すべてのシステムに推奨できるものではなく、個人情報や決済情報を含むWebサイトを運用している場合や、サイバー攻撃による情報漏えいが企業の信用や事業継続に直結するようなデータを扱っている場合など、より高いセキュリティ水準が求められるシステムに対して手動診断を行うのが効果的です。
ツール診断が有効なケースとは?
ツール診断は、短期間で広範囲を自動でチェックできる点が大きな強みです。Webアプリケーション全体の脆弱性を把握したい場合や、定期的なセキュリティ確認を省力的に行いたい場合などに適しています。検査項目が定義化されているため、人的リソースを抑えながらスキャンの再現性を確保でき、社内体制に依存せず一定の品質を維持できるのも利点です。
ツール診断の仕組みや比較のポイントは、脆弱性診断ツールとは?で詳しく紹介しています。
手動診断の強み
手動診断は、セキュリティ専門家がシステムの構造や利用シナリオを把握したうえで柔軟に検証を行えることこそが強みと言えます。診断中の着眼点、報告書の再現手順や修正提案に至るまで、知見が活かされています。次の項目で詳しく説明します。
認証・認可やセッション管理の脆弱性を発見する精度が高い
手動診断は、一般ユーザーが管理画面に到達してしまう、他ユーザー情報を参照・操作できてしまうなどの権限ごとのアクセス制御不備や、ECサイト特有の割引コードの二重適用、キャンセル後の返金フロー不整合などのビジネスロジックの欠陥を実操作に基づいて精査できます。複数権限での画面遷移確認や意図的なパラメータ改ざんなど、状況に応じた手作業により、ツール診断では再現が難しいシナリオでも脆弱性を的確に洗い出せます。
あわせて、セッションID未更新やログアウト後のセッション有効化といったセッション管理の不備も、ログイン/ログアウトの反復や多端末同時ログイン時の挙動確認を通じて検証できます。認証後セッションIDの再生成、同時接続時の制御、ログアウト時の完全無効化などを実際の動作で確認できる点は手動診断の強みであり、より実践的で安全性の高いWebアプリケーションの実現に寄与します。
セキュリティ専門家による脆弱性の説明がある
手動診断では、検出された脆弱性について単なる指摘にとどまらず、対策の観点までセキュリティ専門家が作成する報告書内で説明します。たとえば、入力値検証の不足やアクセス制御の設計ミスといった技術的な要因だけでなく、開発工程での仕様上の前提や運用設定の抜け漏れなど、構造的・運用的な要因まで触れられることもあります。この点はツール診断にはない部分であり、詳細な解説があるのは手動診断ならではと言えます。
また、脆弱性が業務ロジックや権限設計にどのように影響するか、どの程度のリスクがあるかといった実務的な影響範囲も補足されると、開発担当者が具体的な修正方針を立てやすくなります。
修正方法や優先順位の判断についても解説があるため、報告書を「読むだけ」で終わらせず、理解・対策・改善までつなげやすい点が、手動診断ならではの大きな強みです。
手動診断の費用相場
特徴の項目でも触れましたが、手動診断は、セキュリティ専門家がシステムを一つひとつ丁寧に検証するため、診断の精度が高い一方で費用はツール診断と比べてやや高額になる傾向があります。費用は小規模なWebアプリケーションであれば数十万円程度、中〜大規模なシステムや複数のサイトにまたがる診断では100万円以上となるケースもあります。画面数や機能数が多く、診断範囲が広がるほどコストも増加するため、事前に対象範囲を明確にしておくことが重要です。
特に手動診断では、検査対象が広くなるほど費用だけでなく時間もかかる傾向があります。そのため、実際の運用ではコストや時間の都合からすべての画面を診断できず、重要度の高い画面に範囲を絞って実施されるケースも少なくありません。しかし、診断対象外にした画面に脆弱性が残っていた場合、その画面が攻撃の入り口となるリスクもあるため、診断範囲の選定は慎重に行う必要があります。
また、報告書の内容や再診断(修正確認)の有無、打ち合わせの回数、個別の診断項目の追加などにより、見積もり金額が高額になる場合もあります。安価で利用できるツール診断とは異なり、手動診断は高精度な検査と対応力を重視したサービスであるため、費用だけで比較せず、精度・実用性・報告内容まで含めて検討することをおすすめします。
特に、個人情報や機密情報を扱うシステム、また外部企業との連携や対外的な安全性証明が求められるシーンでは、多少コストをかけてでも信頼性の高い手動診断を選ぶ価値があります。
見積もり金額の基本的な算定方法やポイントとなる事柄については、脆弱性診断の見積もりの考え方とは?で詳しく解説しています。
▼社内での検討や上申資料作成に活用いただけるPowerPointテンプレート配布中!
「脆弱性診断実施に関する社内上申用テンプレート」はこちら
https://lp.cscloud.co.jp/va/knowledge/manual-vulnerability-assessment/template/
手動診断にツールも併用して行う
「ハイブリッド診断」とは
手動による脆弱性診断は高い精度を誇る一方で、時間とコストの面で負担が大きくなりがちです。こうした課題を解消する手段として注目されているのが、ツール診断と手動診断を組み合わせた「ハイブリッド診断」です。
ハイブリッド診断とは、まずツール診断で脆弱性の一次スキャンを実施し、その結果を踏まえてセキュリティ専門家が手動で精査・深掘りを行う診断手法です。ツール診断で網羅的なチェックを効率よく行い、検出された内容に対して人の判断を加えることで、診断精度と診断範囲・コストパフォーマンスのバランスを最適化させることができます。
たとえば、OWASP Top 10に代表される一般的な脆弱性についてはツール診断で広範囲にチェックを行い、ログイン機能やビジネスロジックに関する複雑な検証は手動で対応するといった使い分けが可能です。これにより、誤検知や見逃しを最小限に抑えつつ、全体の診断負荷を軽減できます。
さらに、ツール診断の結果を正しく解釈し、適切な対応策を導き出すには専門的なセキュリティ知識が不可欠ですが、ハイブリッド診断であれば診断結果の分析から対応方法の提示までをセキュリティ専門家が担うため、社内に専門的な人材がいない場合でも安心して診断できます。技術的な解説に加え、実装上の注意点や優先順位の判断など、現場目線での具体的なアドバイスが得られるのも大きなメリットです。
ハイブリッド診断なら
「サイバーセキュリティクラウド脆弱性診断サービス」
サイバーセキュリティクラウドでは、セキュリティ専門家による手動診断と広範囲をカバーできるツール診断を効果的に組み合わせた広くて深い「ハイブリッド診断」を提供しています。ビジネスロジックやセッション管理といったツール診断だけでは対応しきれない領域については、豊富な診断実績を持つセキュリティ専門家が一つひとつ丁寧に検証します。
サイバーセキュリティクラウドの脆弱性診断では、以下のような特長があります。
・セッション管理に特化した診断ツールを自社開発した経験を持つスタッフが診断コンサルタントを担当。複雑な認証・認可の構造やセッション制御に関する相談にも対応可能
・他社にはないセッション管理の脆弱性診断項目で、セッションにまつわるトラブルを徹底的に検証
・診断開始前には、システム環境や要件のヒアリングを実施し、診断対象システムの規模やリスクに応じた最適な診断方法や範囲を提案
・検出された脆弱性の修正作業が適切に行われているか確認する再診断を1回無料で実施
セキュリティ専任の人材が不足している企業や、高リスクなWebサービスを運用する企業にとって、準備からアフターサポートまで一貫した対応が受けられるのでおすすめです。